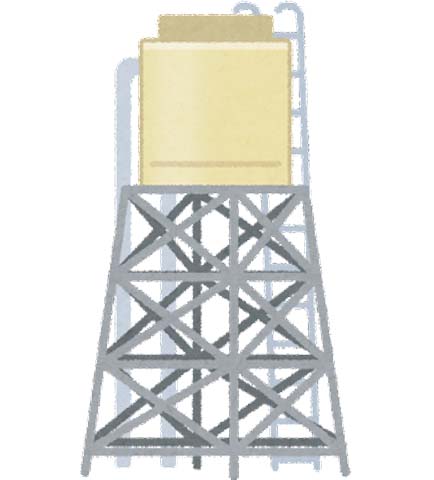保守点検サービス
消防点検
消防法第17条に基づき、消防用設備等を設置することが義務づけられている防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、その設置された消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告する義務があります。消防用設備等は、いついかなる場合に火災が発生しても確実に機能を発揮するものでなくてはいけません。なので日頃の維持管理が十分に行われることが必要となります。
年2回
機器点検(6ヵ月に1回以上) 総合点検(1年に1回以上)
設備点検対象
消火器・自動火災報知設備・誘導灯・避難器具・非常放送設備・消火栓・ハロン消火設備・二酸化炭素消火設備・非常警報設備・連結送水口など
設備点検 報告書の提出
点検を行い、点検報告書を管轄消防署に提出。 不備が出た場合、改修工事が必要となります。
事例 ー 歌舞伎町ビル火災
民事訴訟:ビルオーナーらが約8億6千万円を支払うことで和解 刑事訴訟:ビルオーナーらに業務上過失致死罪で禁固2年から3年、執行猶予4年から5年の有罪判決。
東京都新宿区歌舞伎町の雑居ビルで起きた火災により44人が死亡し、3人が負傷する被害を出しました。多くの死傷者を出した原因は、ビル内の避難通路の確保が不十分であったためとされております。 この事件を機に消防法の違反者の罰則は、従来の「懲役1年以下・罰金50万円以下」から「懲役3年以下・罰金300万円以下」に引き上げられ、法人の罰則も、従来の「罰金50万円以下」から200倍にあたる「罰金1億円以下」に引き上げられています。
- 消防法では消防設備点検の実施と点検結果の報告が義務づけられています。未設置・点検の未実施・虚偽の報告・点検報告をしなかった場合は罰金または拘留が科せられます。必ず点検・報告・改修を行いましょう。
貯水槽清掃
水道法では、貯水槽の有効容量の合計が10tを超える 給水設備を「簡易専用水道」と言います。「簡易専用水道」の設置者には法律上、年に1回以上の貯水槽清掃・水質検査等の管理が義務付けられています。また、賃貸の場合は殆どの場合は10t未満ですが、有効容量の合計が10tを超えない場合でも適切な維持管理をしなければなりません。水質管理の観点からどんなに小さな貯水槽でも1年に1度の貯水槽清掃を実施しましょう。
第1回
年/1回以上の貯水槽清掃及び水質検査などの管理が義務
設備点検内容
周辺の清掃状態・・・・・ゴミ・汚物が散乱していないか、清潔な環境であるか
本体の状態・・・・・・・・・亀裂・劣化している箇所はないか
外壁の状態・・・・・・・・・劣化の状態確認、外側からの光が透過していないか
本体の壁面の状態・・・汚れや異物混入がないか
漏れがないか・・・・・・・外側から雨水や汚水などの侵入がないか
設備点検 報告書の提出
貯水槽の有効容量が10t以上の場合は簡易専用水道検査を実施し、保健所に報告書の提出を行います。
事例 ー 神奈川県平塚市の雑居ビルにおけるクリプトスポリジウムによる集団感染
時期:平成6年8月
事故の概要
ビル関係者736中有症者461人。医療機関受診者77人、入院者5人。ビル内の貯水槽水道により給水された水道水が原因。排水ポンプの故障により、汚水及び雑排水が受水槽に混入、簡易専用水道に該当するが、簡易専用水道として把握されておらず、管理基準に基づく管理もなされていなかった。 貯水槽の管理者は、水槽の清掃を毎年1回以上、定期的に行わなければなりません。これに違反すると、100万円以下の罰金を科せられる。小規模貯水槽水道の設置者には、罰則規定はありませんが、簡易専用水道に準じた管理を行うようにと明記されています。
- 水道法では有効容量が10t以上の貯水槽は定期清掃の実施と検査結果の報告が義務づけられています。また10t未満の貯水槽でも居住者の健康被害防止の観点から定期的な清掃を行いましょう。
エレベーター点検
エレベーターは建築基準法第8条で「建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない」と定められており、点検を怠ると法律で罰せられます。また、エレベーターの耐用年数は20〜25年と言われており、突発的な故障を防ぐためにも定期的な点検メンテナンスは欠かせません。
月1回
年1回の法定点件に加え、月2回、月1回、2ヶ月に1回などの周期で行う定期点検。
設備点検内容
国土交通省の定める資格を有する者などに1~3カ月に1回、機械室、制御器、巻上機、かご、乗場、昇降機、ピット等の点検・整備を行います。
設備点検 報告書の提出
法定点検の結果をもとに昇降機定期検査報告書を作成し、昇降機に関する地域法人などを経由して特定行政庁に報告します。
メンテナンス契約について
POG(パーツ・オイル・グリース)契約
定期的な機器・装置の保守点検のみをおこなパーツやオイルなどの消耗品以外は別途費用が掛かります。
FM(フルメンテナンス)契約
修理費は月々の保守料に含まれており、突発的な修理、部品交換やワイヤー取替え工事代金などの心配がありません。
- 建築基準法第8条で常時適法な状態で維持することが義務となっています。点検を怠ると法律で罰せられますのでしっかりと点検・報告書の提出を行いましょう。
キュービクル点検
キュービクルなどの事業用電気工作物・自家用電気工作物を使う事業者は、定期的な自主点検をすることが電気事業法で義務付けられております。点検を怠ると構内全体が停電するだけでなく、近隣一体を巻き込んだ停電が発生したり、感電事故や火災などの人命に関わるような重大な事故も起きかねません。電気は目に見えない分、それだけ保安点検は重要であると言えるでしょう。
月1回
キュービクルに絶縁監視装置を取り付け安全性を高めている場合は隔月での点検
年次点検 年1回
設備点検内容
月次点検項目(キュービクルを停電させないで点検)
・キュービクル、区分開閉器等の外観目視点検
・漏えい電流測定
・受電盤
・配電盤の電圧、負荷電流測定
・受電盤
・配電盤のブレーカー温度測定
・非常用発電機の手動での起動
・停止確認 など 年次点検項目(キュービクルを停電させて点検)
・停電状態での電気設備の精密な点検
・キュービクル、区分開閉器等の外観目視点検
・絶縁抵抗測定
・保護継電器動作特性試験
・保護継電器連動動作試験
・蓄電設備の電圧
・比重
・温度測定
・非常用発電機の自動での起動
・停止確認
トランス・コンデンサ等 のPCB検体検査
キュービクルの中には、「変圧器(トランス)やコンデンサ等」の電気機器が設置されています。それには特別管理産業廃棄物であるPCBが含まれている可能性があり、適切な管理・処分が必要です。
高濃度PCB廃棄物の処分期間は 令和4年 3月31日まで 低濃度PCB廃棄物の処分期間は 令和9年 3月31日までとなっております。 含有の有無は絶縁油を採取して、検体検査を行うことでわかります。検査は当社で実施可能ですのでご相談ください。
点検を怠ると発生するトラブル
【停電事故】
小動物や雨水が電気設備へ入ったことが原因となり、停電事故につながるケースは少なくありません。
オフィスビルや工場で停電事故が起きれば、その間は電気を使用できなくなってしまうため、業務に支障を来すなどのリスクがあります。
【波及事故】
キュービクルなどの電気設備の故障で停電が起きた場合、電力会社の配電線を通って近隣に停電が広がることもあります。波及事故の影響範囲が、近隣の住宅や工場、病院、銀行、交通システムにも及ぶと、多額の損害賠償が発生する恐れがあります。
【感電火災事故】
キュービクルなどの電気設備からの漏電が、感電事故につながる場合もあります。また、漏電から火災事故に発展するケースも少なからず存在するため、キュービクルの不具合が原因で尊い人命が失われる可能性は決してゼロだとは言い切れません
- 電気事業法で設置者は維持及び運用に関する保安規定を定めそれを守り、経済産業大臣に届けることが義務となっています。また、電気主任者の選任も義務であり、しっかりと点検を行いましょう。